概要
小泉八雲著の『茶碗の中』です。
オリジナル版は1902年に出版された『骨董』の中に収録されています。
ここには田部隆次訳版を全文転載します。
※データは青空文庫様から頂いております。青空文庫様ありがとうございます。
本文
茶碗の中 / IN A CUP OF TEA
小泉 八雲 著
田部 隆次 訳
読者はどこか古い塔の階段を上って、真黒の中をまったてに上って行って、さてその真黒の真中に、蜘蛛の巣のかかった処が終りで外には何もないことを見出したことがありませんか。あるいは絶壁に沿うて切り開いてある海ぞいの道をたどって行って、結局一つ曲るとすぐごつごつした断崖になっていることを見出したことはありませんか。こういう経験の感情的価値は――文学上から見れば――その時起された感覚の強さと、その感覚の記憶の鮮かさによってきまる。
ところで日本の古い話し本に、今云った事と殆んど同じ感情的経験を起させる小説の断片が、不思議にも残っている。……多分、作者は無精だったのであろう、あるいは出版書肆と喧嘩したのであろう、いや事によれば作者はその小さな机から不意に呼ばれて、かえって来なかったのであろう、あるいはまたその文章の丁度真中で死の神が筆を止めさせたのであろう。とにかく何故この話が結末をつけないで、そのままになっているのか、誰にも分らない。……私は一つ代表的なのを選ぶ。
*
天和四年一月一日――即ち今から二百二十年前――中川佐渡守が年始の𢌞礼に出かけて、江戸本郷、白山の茶店に一行とともに立寄った。一同休んでいる間に、家来の一人――關内と云う若党が余りに渇きを覚えたので、自分で大きな茶碗に茶を汲んだ。飲もうとする時、不意にその透明な黄色の茶のうちに、自分のでない顔の映っているのを認めた。びっくりしてあたりを見𢌞したが誰もいない。茶の中に映じた顔は髪恰好から見ると若い侍の顔らしかった、不思議にはっきりして、中々の好男子で、女の顔のようにやさしかった。それからそれが生きている人の顔である証拠には眼や唇は動いていた。この不思議なものが現れたのに当惑して、關内は茶を捨てて仔細に茶碗を改めてみた。それは何の模様もない安物の茶碗であった。關内は別の茶碗を取ってまた茶を汲んだ、また顔が映った。關内は新しい茶を命じて茶碗に入れると、――今度は嘲りの微笑をたたえて――もう一度、不思議な顔が現れた。しかし關内は驚かなかった。『何者だか知らないが、もうそんなものに迷わされはしない』とつぶやきながら――彼は顔も何も一呑みに茶を飲んで出かけた。自分ではなんだか幽霊を一つ呑み込んだような気もしないではなかった。
同じ日の夕方おそく佐渡守の邸内で当番をしている時、その部屋へ見知らぬ人が、音もさせずに入って来たので、關内は驚いた。この見知らぬ人は立派な身装の侍であったが、關内の真正面に坐って、この若党に軽く一礼をして、云った。
『式部平内でござる――今日始めてお会い申した……貴殿は某を見覚えならぬようでござるな』
甚だ低いが、鋭い声で云った。關内は茶碗の中で見て、呑み込んでしまった気味の悪い、美しい顔、――例の妖怪を今眼の前に見て驚いた。あの怪異が微笑した通り、この顔も微笑している、しかし微笑している唇の上の眼の不動の凝視は挑戦であり、同時にまた侮辱でもあった。
『いや見覚え申さぬ』關内は怒って、しかし冷やかに答えた、――『それにしても、どうしてこの邸へ御入りになったかお聞かせを願いたい』
〔封建時代には、諸侯の屋敷は夜昼ともに厳重にまもられていた、それで、警護の武士の方に赦すべからざる怠慢でもない以上、無案内で入る事はできなかった〕
『ああ、某に見覚えなしと仰せられるのですな』その客は皮肉な調子で、少し近よりながら、叫んだ。『いや某を見覚えがないとは聞えぬ。今朝某に非道な害を御加えになったではござらぬか……』
關内は帯の短刀を取ってその男の喉を烈しくついた。しかし少しも手答がない。同時に音もさせずその闖入者は壁の方へ横に飛んで、そこをぬけて行った。……壁には退出の何の跡をも残さなかった。丁度蝋燭の光が行燈の紙を透るようにそこを通り過ぎた。
關内がこの事件を報告した時、その話は侍達を驚かし、また当惑させた。その時刻には邸内では入ったものも出たものも見られなかった、それから佐渡守に仕えているもので『式部平内』の名を聞いているものもなかった。
その翌晩、關内は非番であったので、両親とともに家にいた。余程おそくなってから、暫時の面談をもとめる来客のある事を、取次がれた。刀を取って玄関に出た、そこには三人の武装した人々――明かに侍達――が式台の前に立っていた。三人は恭しく關内に敬礼してから、そのうちの一人が云った。
『某等は松岡文吾、土橋久藏、岡村平六と申す式部平内殿の侍でござる。主人が昨夜御訪問いたした節、貴殿は刀で主人をお打ちになった。怪我が重いから疵の養生に湯治に行かねばならぬ。しかし来月十六日にはお帰りになる、その時にはこの恨みを必ず晴らし申す……』
それ以上聞くまでもなく、關内は刀をとってとび出し、客を目がけて前後左右に斬りまくった。しかし三人は隣りの建物の壁の方へとび、影のようにその上へ飛び去って、それから……
*
ここで古い物語は切れている、話のあとは何人かの頭の中に存在していたのだが、それは百年このかた塵に帰している。
私は色々それらしい結末を想像することができるが、西洋の読者の想像に満足を与えるようなのは一つもない。魂を飲んだあとの、もっともらしい結果は、自分で考えてみられるままに任せておく。
1937(昭和12)年1月15日発行
※「旧字、旧仮名で書かれた作品を、現代表記にあらためる際の作業指針」に基づいて、底本の表記をあらためました。
その際、以下の置き換えをおこないました。
「或は→あるいは (て)居る→い (て)置→お 又→また (て)見→み」
※以下の語に底本にはないルビを追加しました。
「殆んど 身装 甚だ」
入力:館野浩美
校正:大久保ゆう
2019年11月24日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(https://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。当サイトでの変更内容:
上記のファイルの”※(「廴+囘」、第4水準2-12-11)”を”𢌞”の漢字に変更。
文章転載元
青空文庫:https://www.aozora.gr.jp/cards/000258/files/59429_69744.html
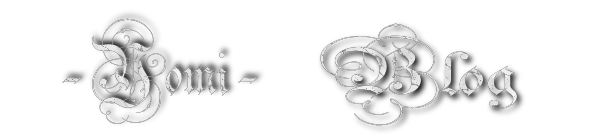



コメント