概要
山宮允が著した「小泉八雲の生涯」です。
1950年に出版された小峰書店の『耳なし芳一』の中に解説文として収録されています。
本文
小泉八雲の生涯 山宮允著
1
世界地図をひろげてみると、ギリシャの西北には、アイオニア群島という島島が散在している。その島島の中の一つに、ギリシャ人がレフカダと呼んでいる、特に美しい島がある。その島は、南国の明るい日光のもと、肥沃な土地にぶどう畠やオリーヴの林があり、山には大きな木が繁茂している。この島には、有名なアポロの殿堂があり、むかし、手足に何十羽という鳥をしっかりむすびつけ、からだが軽く落ちてゆくようにして、罪人を高い崖から投げ落したというような話さえ、伝わっている。
この本の原著者ラフカディオ・ヘルン(小泉八雲)がこの島に生れたのは、一八五〇年六月二十七日で、ラフカディオはこの島の名にちなんでつけた洗礼名である。
ヘルンの父親チャールズ・ヘルンは、英国の軍艦で、一八四六年、その頃英国の保護領だった、アイオニア群島の一つに来任し、その土地の娘ローザ・テッシマと「小説的」な結婚をした。そして、三人の男の子をもうけた。へンはその中のひとり、チャールズ・ヘルンの二男である。一八五一年の末、父親チャールズが西インドに転任することになった時、ラフカディオはまだ二歳になっていなかった。ラフカディオは、母親と、通訳をかねた若い女中につれられて、父親の故鄕、英国アイルランドのダブリンに渡った。
ダブリンには、チャールズ・ヘルンの母方の叔母にあたるサリー・プレネーンという、ローマ旧教の信者で資産のある未亡人がいて、ラフカディオをもらいうけて相続人にしようとした。そこで、ラフカディオは、母親とともに、ダブリンの郊外にあるプレネ1ンの邸宅に移り住むことになった。
一八五三年、ラフカディオの父はダブリンに帰ってきたが、やがて、「小説的」た結婚も悲劇に終り、離縁された母のローザは、ラフカディオに別れて、さびしく故国ギリシャへ帰って行った。その後ラフカディオは、母に対してやるせない思慕の念をいだきつづける人となった。
母との生別に心をくじかれたラフカディオは、大叔母の世話になって成長した。大叔母はラフカディオを愛し、ラフカディオも大叔母によくなついた。富裕な大叔母は夏になると、ラフカディオをつれて、セント・ジョージ海峡を渡って、対岸ウェィルズのバンゴアに行った。バンゴア附近の古いお城で、ラフカディオがはじめて東洋の美術を見たのもその頃だった。
ラフカディオは、神経質で、ものの好ききらいがはげしくて、暗い室内に寝ているときに、よく、幽霊を見るような子供であった。そして、英国の上流社会の慣習にしたがって、初歩の教育を家庭教師によってさずけられた。
一八六三年の秋、ヘルンは、英国ダラムのアンショウ・コリジに入学した。それは、歴史の古い、設備のととのったローマ旧教の学校だった。ヘルンは画と読書が好きであり、物に感じやすい少年でりっぱな詩を書いた。作文がいつも抜群の成績で、学校での生活は愉快であった。
ヘルンは生来強度の近視眠であったが、この学校で学友と遊んでいた時、学友が投げたなわが左の目にぶつかって、それが因で失明した。ヘルンは二度半という強度の近視で、それに背も低かったので、自然、内気になってしまった。後年日本に来た時に、日本人が背が高くないので、ヘルンはうれしくてならなかった。
大叔母が、投資した事業に失敗したために、ヘルンはアンショウ・コリヂを退学しなければならなくなった。破産した大叔母は、大叔母を破産させた親戚のモリヌークス家の一員として、アイルランドのトレモアに移り住んだ。そこは湾にのぞむ海岸にあって、景色がよかった。へルンの「海を愛する心」が、ウェィルズの・バンゴアや、このトレモアで養われた。ヘルンは運動は好きでなかったが、水泳だけは得意であった。
ヘルンはその後ロンドンに出たことがある。それはテニスンやプラウニングやロゼッティやラスキンが、文壇に、はなやかに活動していた頃である。
2
ヘルンは、モリヌークスのはからいで、フランスのローマ旧教の学校に留学したが、そこではむしろ不幸であった。それが原因となり、ヘルンは、すっかり、ローマ旧教のきらいな人になった。その頃、フランスの文壇には、ゴウティエや、ヴィクトル・ユーゴーや、フローベールや、ポードレーが活動していた。
ヘルンは、そこで、一八六九年、モリヌークスの親戚をたよって、アメリカのシンシナティへの旅に上った。
ニュー・ヨークにしばらくいてから、シンシナティに到着したが、大叔母からの送金がまもなく絶えて、ヘルンはひどく困窮してしまった。ヘルンは、やむなく、それから一年半ばかりの間、行商人の手助けや、電報配達や、宿屋の給仕などをして暮していたが、その間も、たえず図書館へ通って本を読み、かたわら作文にもいそしんだ。
その後、英国出身のヘンリー・ワトキンという活版屋にしばらくつとめた。それから、一八七四年『シンシナティ・インクァイラー』紙の記者となった。ヘルンは仕事に熱心で、書く文章は流灑であった。探訪や三面記事の係であった。
一八七六年、『コンマーシャル』紙の社員になった。この頃、ヘルンはすでに哲学や、宗教や、文学や、科学や、そうとう深い修養を積んでいた。収入はわずかであったが、衣食の費用を節約して、しきりに本を買った。ヘルンが、夜も眠らないで、フランスの文学をつぎつぎに英語に訳したのもその頃だった。
ヘルンは、やがて、新聞事業に興味を失った。そして、南方の空気や景色にあこがれて、一八七七年の秋、ミシシッピイ河を下って、ニュー・オルリァンスに移った。
ヘルンは、そこから、『コンマーシャル』紙に通信を寄せていたが、ヘルンの書く文章があまり文学的だったので、多くの読者はそれを好まなかった。ヘルンは、そこで、またもとの貧困にもどった。本も売り、衣服も売った。二日間に一どしか食事をしなかったこともある。
一八七八年の夏、ヘルンは、小新聞『ディリー・アイテム』に入社した。そこでは、さいわい、勤務時間が少なかった。ヘルンは、勉強の時間が多くなったのをよろこんだ。
一八八一年の冬、ニュー・オルリァンスの二つの新聞が合同して、『タイムズ・デモクラット』という大新聞ができあがった。へルンはそこへ、文芸部長として、迎えられた。それからは、文芸関係の記事を書くだけでよかったので、ヘルンはようやく自分の世界を見出したように感じて喜んだ。ヘルンは、同紙上に、百八十七篇の外国文学の翻訳を連載した。
一八八四年、ニュー・オルリァンス百年祭記念博覧会が開かれた。その時ヘルンは日本から来た事務官、服部一三に会った。ヘルンは、この博覧会に関する記事数篇を『ハーパー雑誌』に発表した。
へルンは、ニュー・オルリァンスに移住後の十年間に、何冊かの文学的著作を出版し、知名の文人になった。しかし、そうなっても、「波止場に出て船はかりを眺めている」心持、生涯旅を続けようという、生来の放浪的精神が、いつもヘルンを離れなかった。
3
一八八七年の夏、ヘルンは、シンシナティを経て、ニュー・ヨークに出た。しかし「ここにいると眼がくらみ、耳がきこえなくなり、息ができなくなり、おそろしくなってくる。」といって、ヘルンはまもなく仏領西インドのマルティニーク島サン・ピエルにおもむいた。そこは自然がすばらしい色彩と光輝に充ちていた。ヘルンはそこで原稿を書き、資料を集めた。
一八八九年の晩春に、ヘルンはふたたびニュー・ヨークに出た。それからフィラデルフィアへも行ったが、職を得るためにまたニュー・ヨークに戻ってきた。
ニュー・ヨークには、ヘルンが以前から通信を送っていた『ハーパー雑誌』がある。ヘルンがその美術主任であるバットンを知るに至ったのは、その頃だった。ヘルンはバットンから、日本の美術や文学に関する書物をいろいろ見せられた。ヘルンはバットンに、日本に行く機会を得たい。そして、「日本に関する普通の書物に書いてないこと」を書いてみたいといって相談した。このバットンのはからいでヘルンは日本に来ることになった。ウェルドンという画家が、ヘルンに同行することになった。
4
時速十三マイルの小汽船「アビシニア」号が、ヴァンクーヴァーから、十七日もかかってようやく横浜に入港したのは、一八九〇(明治二十三)年四月四日のことである。富士山が見えた。点点見える舟の白帆が美しかった。白いかもめが数限りなく飛んでいた。
「自分はここで死にたい!」
と、ヘルンはいった。
ヘルンは、スーツ・ケースとハンド・バッグを左右の手に下げて上陸した。その中には、ポケット用のインクつぼ、ペン、三本のペン軸等もはいっていた。日本のさくらも、もうそろそろ咲きそめていた。
ヘルンにとって、日本の風物はまったく珍奇なものであった。日本は西インドとは比較にならぬ変った、複雑な国であった。ヘルンは深い興味を覚えた。そして、この国の研究には、長い時日が必要であると思った。
ヘルンは、この日本で自由な身になるために、五月のはじめに、ハーパーの特派員をことわった。
そして、日本にきて交際することになったチェンバレンや、前にニュー・オルリァンスの博覧会で知り合った服部一三(文部省普通学務局長)の世話で、出雲の松江中学校に英語教師として赴任した。
5
出雲は大昔から有名な国である。古い日本を知ろうとするヘルンには、住むにふさわしい土地であった。ヘルンは松江中学校に迎えられた、ふたりめの外人教師で、少しばかり師範学校へも講義に出た。
それは、明治初年の欧化思想更生の時期で、どの土地の中学校にも、英米人の雇教師がいたが、それら教師は、多く、日本人を蔑視し、英米の風俗や習慣を誇っていた。しかし、ヘルンには少しもそういうところはなかった。ヘルンは日本がたまらなく好きであった。日本人がつまらないと思うものまで、ヘルンは好んだ。松江の人たちはそれを知って、はじめはずいぶんふしぎに思ったが、やがて、みんなあらためて感心した。そして、松江の人が、みな「ヘルン先生」を敬愛するようになった。
その頃の松江には、電灯もなく、ガスもなく、ストーヴもなかった。しかし、湖水のほとり、出雲富士を近くに望む風光はすぐれていた。そして、ヘルンには、その松江が、たしかに現実と幻想とが織りなしたすばらしい楽園であり、蜃気楼の町であった。ヘルンは、ここに、アメリカでのはげしい苦労をすっかり忘れて、安住した。
ヘルンが松江に来た当座は、材木町の宿屋にいた。それから、やがて、末次本町の二階建の家を借りた。その家は大橋川にかかっている大橋の近くにあって、美しい湖も眺められた。霜におおわれた橋の上をカラコロと渡り行く下駄の音さえ、ヘルンをたいへん喜ばせた。
ヘルンは、暇あるごとに、松江の町をあるきまわった。幸福だった。骨董や浮世絵を買いもとめた。市内や郊外の寺や、神社や、旧跡をたずねては、研究に余念がなかった。中学校では「ぼたん」、「きつね」、「蚊」、「ゆうれい」、「かめ」、「ほたる」、「ほととぎす」といったようた題を出して、生徒に英語の文章を書かせた。
その年の末、ヘルンは、松江の藩士小泉湊の娘節子と結婚した。
翌一八九一(明治二十四)年の元旦、ヘルンは日本の習慣にしたがって、はおり、はかまで、年始 まわりなどをした。定紋にはヘルンの祖先と同じように、さげ羽の鷺(へロン)がついていた。へルンという名は鷺(ヘロン)から出たのである。
ヘルンはその春北堀町に転居した。城のお堀のすぐそばの屋敷で、山を背にして広い庭があり、その庭には池があった。ヘルンは浴衣を着て、うれしそうに、その庭を、庭下駄をはいて散歩した。そんな時、山ばとや、がまや、ヘびが、ヘルンのよい遊び友だちだった。その庭からは、天守閣も眺められた。
ヘルンは生徒や教師とも親しく交際し、いろんな会合にも出席した。そのかたわら、多くの論文や小説を書きつづった。
6
しかしながら、日本海をおし渡って、松江に吹きつける真冬の風は、ヘルンにはたえがたかった。身を切られるような心地がした。ヘルンが南方に住みなれていたからである。ヘルンはそのために、自分の眼がひどく悪くなるのを感じた。それで、ついに、ヘルンは熊本の第五高等中学校に転任することにした。
生徒一同、教師、父兄、市民の有志、県の高官、――みんなそろって、ヘルンを波止場まで見送った。一八九一(明治二十四)年の晩秋のことである。
熊本第五高等中学校には、外人官舎があったが、日本間のついていないその官舎が、ヘルンの気に入らなかった。そこで、ヘルンは、純日本風の借家にはいった。広いよい庭のある家だった。
熊本の風景は、男性的で、松江のようた優雅な趣はなかった。
ヘルンは、学校では、英語とラテン語、そのほか時にはフランス語などもうけもって、一週二十七時聞の授業をした。生徒が書いた作文なども、たんねんになおしてやった。
一八九二(明治二十五)年の春休みには大宰府、夏休みには博多、門司、神戸、京都、奈良、隠岐などに旅行した。翌年の春休みにはまた博多へ、夏体みには、長崎に旅行した。
「西洋の子供よりも日本の子供のような」長男一雄が誕生したのは、一八九三(明治二十六)年の秋であった。ヘルンは、「自分のからだがふたつあるような」妙な感じがしたのだった。そして、この時から、ヘルンは自分の責任がいっそう重くなったことを感じて、いっそう勉強家になったのである。
一八九四(明治二十七)年の春休みには、讃岐の金比羅宮に参詣し、夏には東京、横浜に、旅行して、一雄のために、高価なおもちゃやうば車を買って帰った。
やがて三年の約束の期限が来て、ヘルンは熊本を去り、『神戸クロニクル』の記者になって、神戸に移った。
7
ヘルンは、神戸に美しい旧日本のすがたを見ることができなかった。神戸はなじみにくい、欧州文明の皮相をまねた新開地で、外人がいっぱいいた。ヘルンは、白いシャツも、洋服も、きらいであった。やわらかいたたみの上の、しとやかで、礼儀ただしく、質素で、清らかな日本の生活が好きであった。
ヘルンは一八九五(明治二十八)年の春に、京都に行った。その秋ふたたび京都に行き、奠都千百年祭を見た。
ヘルンは、いつも、妻子一族の未来を思った。そして、前から、日本に帰化しようと思っていた。
そして、その手続をして、小泉八雲と称した。小泉は夫人の生家の姓、八雲の名は、日本古歌「八雲立つ出雲八重垣」からとった。
ヘルンは、当時四十五歳になっていた。そして、父としての責任を強く感じて、いっそうはげしく勉強するようになった。寸陰をも惜んで勉強をつづけた。『心』や『仏土の落穂』を書いたのもその頃だった。それらはヘルンの日本に関する著作の中で、とくに有名なものである。
8
一八九五(明治二十八)年ヘルンは、知人チェンバレンを介して、東京帝国大学から英語、英文学の講義担当の依頼をうけた。東京帝大の外山学長の懇望によるものだった。ヘルンは考慮の末、ついに上京を決意した。
ヘルンは、翌一八九六(明治二十九)年の夏、なつかしい出雲に旅行して、神戸に帰った。そして、夏の終りに、上京した。
ヘルンが東京に定めた新居は、市ガ谷の高台の上にあった。その新居の地続きには、墓地があった。それは、一六四〇(寬永十七)年に創建された瘤寺(俗称)の墓地であった。境内には、多くの古い杉の木が、昼なお暗いほどに茂っていた。ヘルンはこの慕地がたまらなく好きだった。
大学では、週十二時間講義した。毎週木曜日、十二時から午後二時まで休憩時間があったので、その時間を利用して、ヘルンは上野の森へ行った。そしてそこの精養軒で、夫人といっしょに昼食するのが例であった。木曜日は夫人の外出日でもあり、その時刻に、夫人がいつも精養軒に来ることになっていた。
その帰りみち、ヘルン夫妻は、その頃竹の台にあった商品陳列館に立ちよったりした。そこでは、ヘルンが日本語で値段を聞いたのに、英語で答える女店員におどろいて、ヘルンは、買ものをやめてしまったことなどあった。
一八九七(明治三十)年の春に、二男巌が生れた。厳の名は、大山大将に因んでつけたものである。巌は後に母方の親戚の家に入り稲垣姓を冐した。
ヘルンは、その夏、家族とともに、一週間ばかり静岡県の焼津に行った。焼津では、魚屋の山口乙吉の二階を借りた。ヘルンは、深くて荒い焼津の海がたまらなく好きになった。東京への帰り途、ヘルンは、藤崎という士官候補生といっしょに富士登山をこころみた。
一八九八(明治三十一)年の夏、ヘルンは、家族とうちつれて、一カ月間神奈川県の鵠沼に、翌一八九九年の夏は、ふたたび、焼津に、行った。その年の暮、三男清が生れた。
それから、ヘルンは、一九〇〇(明治三十三)年、一九〇一年、一九〇二年、一九〇四年と、つづけて焼津に行って夏を過した。長女壽々子が生れたのは、一九〇三(明治三十六)年の秋である。
ヘルンは暑い気候を好んだ。だから、焼津へは、避暑のために行ったわけではなく、泳ぎに行ったのである。ヘルンにとって、焼津は、松江や隠岐と同じように、旧日本を見ることのできる土地であった。
ヘルンは、その頃、アメリカの友人への手紙にこう書いた――
「神様は東京にはお留守たから、海岸へでも行ってさがすことにします。」
そして、焼津を「神様の村」といっていた。
ヘルンは、焼津では、長男を教えることと、一日に三ど泳ぐことが、日課であった。雨の日にもヘルンは泳いだ。嵐の時は、海岸へ出て、荒れ狂う波に飽かす眺め入った。夕方には、子供たちといっしょに、「ゆうやけこやけ」を合唱した。
近所の子供たちを集めて話をさせていたある晩のこと、長男が、ひとりの子供の話の最中、そばにあった画本を手にとりあげて眺めていた。おそらくへルンの長男には、その子の話がおもしろくなかったのであろう。ヘルンは、あとになってから、その長男をいましめてこういうた――
「ああいう態度はよくないです。あなたは無礼いたしましたから、あやまりなさい。」
そして、ヘルンは、長男をその子の家へあやまりに行かせた。
焼津はその後ずいぶん変ってしまった。しかし、焼津の人たちは、
「贈従四位小泉八雲先生諷詠之地」
いう碑をたて、ヘルンを永久に記念している。
9
前にも書いたが、ヘルンは、焼津と同様に、市ガ谷の家の隣にある瘤寺の森を愛した。当時のヘルンは、ほんとうに、その森と焼津とだけが、詩の神の仕み家であると思っていた。
だが、ある日、瘤寺の森の中で、三本の杉の大木がきりたおされた。ヘルンは、すぐに、瘤寺にこう申し入れた――
「杉の木を切らなくてすむものなら、私のカのおよぶかぎり瘤寺を助けさせていただきます。」
しかし、杉の大木は、つぎからつぎへときりたおされることになった。墓地をほかの土地へ移して、そこを貸地にし、貸家を建てる計画だったからである。
ヘルンは古い杉の木がきりたおされる音を聞いて、自分の手足を切られるように切ない思をした。
ヘルンが東京へ出たことは、ひとえに、ヘルン夫人の希望に添うためであった。ヘルン夫人は、年来、東京を見たがっていたのである。
ヘルンは、東京は地獄のようなところだといっていた。夫人の希望に添い、夫人に東京見物をさせるつもりで東京へは出たものの、ヘルンは、やはり、東京が好きになれなかった。ヘルンは夫人にむかって、「あなたの見物がすみましたら、田舍にまいります。」とたびたびいった。そして、やがてはいなかにしりぞいて一生を送りたいと思っていた。ヘルンはよく晴れた朝の空や、霞や、小さいお宮のお祭や、かえるが鳴いている水田や、笠をかむった百姓や、八百屋や、漁夫や、巡礼などが好きであった。ヘルンの愛する美の世界は、「純粋の日本」の中にあった。だから、ヘルンは、夫人がヘルンに家を買う話を持ちかけるたびごとに、夫人に答えて、「家を買うのなら、松江か隠岐にいたしましょう。」といった。しかし、今、ヘルンは、瘤寺の森がきりたおされることにきまって、力をおとしているところであった。そしてヘルンは、西大久保によい売家があるということを、夫人に聞かされて、その家を買う気になった。それはある子爵の屋敷で、広い庭にはりっぱな木や、花や、竹やぶがあった。ヘルンは一九〇二(明治三十五)年の春、そこに移った。そして、ヘルンは、その家から大学に通い、戸山ガ原や、高田馬場や、目白台、雑司ガ谷、落合、新井の方面をよく散歩した。
10
ヘルンは、大学では、「ほんとうにまじめで、その上世慣れた、たいそう親切で、卒直な」外山博士が好きであった。その外山学長は、やがて大学総長になり、それから文部大臣になり、まもなく辞職して、一九〇〇(明治三十三)年の春に永眠した。外山博士の葬式には、ヘルンも参列したが、ヘルンが日本で葬式に参列したのは前にも後にもこの時だけであった。そして、外山博士の歿後、ヘルンは、大学に不安を抱くようになった。
ヘルンは、自分を、キリスト教信徒から悪評をうけている人間だと考えるようになった。社会と、教会と、そして英米を批評する人たちが、自分を苦しめるのだと思いこんだ。ヘルンは、ほんとうに普通の人なら何でもないようなことがらにも、深くなやまねばならないような性質の人であった。ヘルンがとても無邪気で、正直で、純真で、どうしても、自分の感情をごまかすことができない種類の人だったからである。
ヘルンは狐立の境地におちいった。交際がきらいになった。人間がきらいになった。大学では、教官室に出入りしなくなった。
しかしながら、ヘルンはたえず大学の教壇から、あたらしい講義をするために努力し、苦心した。そして、寸陰もおしんで、びたむきに著述をつづけた。
ヘルンはついに、一九〇三(明治三十六)年の春に東京帝大をやめた。ヘルンから教えを受けた学生たちは、留任の運動をしたが、ついにヘルンを大学にひきとめることができなかった。
ヘルンは、この時までに、『霊の日本』、『影』、『日本雑事』、『骨董』、『日本お伽囃』などを書いていた。
ヘルンが大学を去った時に、ヘルンの上に、世界中の同情があつまった。やがて、アメリカの諸大学から、ヘルンに講演をたのんで来たが、ヘルンはその時病気であった。病気がなおるのを待ちかねて、ヘルンは、いっしょうけんめい、『神国日本』を書きつづけた。それは、ヘルンが外国の大学で講演する材料を一冊にまとめたものであり、日本精神の歴史であり、日本の将来の予言であった。
『怪談』と『天の河縁起』の大部分は、大学をやめたヘルンが、刻苦精励して一年あまりの間に書きあげたものである。
――『神国日本』を書きあげた時、ヘルンは、早稲田大学から招かれた。一九〇四(明治三十七)年の春のことだった。ヘルンは、早稲田で、松江在住当時の心持をとりもどした。
ヘルンは、ある日、招かれて高田総長の家へ行った。玄関にヘルンを出迎えた総長夫人は、英語でたく、日本語で、「よくおいでくたさいました。」とあいさつした。これがひどくへルンの気に入って、西大久保の家へ帰ると、玄関で靴もぬがずにすぐさま夫人にその話をした。
ヘルンが東京帝大をやめた一九〇三年の春、二男が大久保小学校に入学した。早稲田に行った一九〇四年の春には、長男が二男と同じ小学校の上級に編入された。――その年の秋、ロンドン大学から講演をたのんで来た。その依頼の手紙には、オックスフォード大学も講演をたのむことになっていると書いてあった。しかしそのときすでに、ヘルンの死期がせまっていた。へルンは、その頃、『神国日本』の出版を待ちかねて、「今アメリカであの本の活字を組んでいる音がカチカチ聞えます」といっていた。そして、九月二十六日の朝、ヘルンは、長い長い旅に出た夢をみた。それからその朝、長男が学校に行く前に、ヘルンに
「グッド・モーニング、パパー」
というと、ヘルンは、「プレザント・ドゥリーム!」
と答えた。ヘルンは、どうしたものか、その朝、朝と夜をとりちがえていたのである。「プレザント・ドゥリーム!」(よい夢をごらん!)は、ヘルンの家での、床につく時のあいさつの言葉だった。
それから、ヘルンは、松江時代の教え子であり、当時満州軍総司令部勤務であった藤崎大尉に慰間としておくるの本をあれこれとさがしてから、同大尉に手紙を書いた。その手紙が、ヘルンの絶筆となったのである。ヘルンは、その夜、狭心症で永眠した。享年五十五歳、文学者として、正に円熟期にはいったばかりであった。
ヘルンは、生前ヘルンが愛していた瘤寺に葬られた。そして「正覚院浄華八雲居士」の墓は、雑司ヶ谷墓地に建てられた。
時、あたかも、日露戦争の最中だった。ヘルンは戦争の結果を見ないで永眠してしまった。
1950(昭和25)年6月20日発行
入力:Yomi
2022年9月27日作成

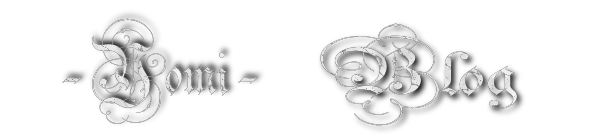



コメント