概要
小泉八雲著の「蓬莱」です。
1904年に出版された小泉八雲著の『怪談』の中に収録されています。
本文
蓬莱(ほうらい)
小泉 八雲 著
山宮 允 訳
深い青色は高空に消え、――水と空は明るいもやのかげにとけ合っている。日は春、時は朝。
ただ空と水――青色のとても広い世界……前にはさざ波、白銀の光とたわむれ、白波の糸は渦巻きおどっているが、すこしむこうは動くものが一つもなく、色のほかには何物もない。温くくかすんだ青い水は、ひろがるままに青空にとけ入り、水平線はない――虚空に高まる距りがあるばかり――はてしなきくぼみが前方にあり、大いなる蒼空は頭上にあり――色は高くなるにつれ深くなる。しかし中ほどの青色の中に、角のある、三日月形にそった屋根のある宮殿の楼閣がかすかに見える――これこそ、記憶のようにものやわらかな日光にかがやく、珍らしい昔の栄華のまぼろしであろうか。
……かように私が述べようとしていたのは掛物なのです――それは私の家の床の間にかけてある、絹地に描いた日本画なのです。そしてその題名は「蜃気楼」というのです。その蜃気楼の形はまぎれもない貴い蓬莱の光明門と、龍宮城の三日月形の屋根です――そして、その描き方は(現代の日本画の筆法で描いてはあるが)千百年以前の支那の描き方です。
当時の支那の書物には、龍宮城のことが次のように書いてあります――
蓬莱には、死亡もなければ苦痛もなく、又冬もない。蓬莱では花はけっしてしばむことなく、木の実の絶えることもない。そしてただの一どでもその木の実を食べたら、けっして二どと飢えや渇き感じることはない。蓬莱には相隣子とか、六合葵とか、万根湯などというふしぎな木が生えていて、万病がなおる。又そこには養神子といって、起死回生の魔法の草がある。その草には、一滴飲めば永遠の若さを保つという、神泉の水がかけてある。蓬莱のひとびとは、よくよく小さな茶わんで御飯を食べる。しかし――どんなにたくさん食べても――食べ手が十分だと思うほど食べても、茶わんの飯は減らない。又蓬莱の人は、よくよく小さな杯で酒を飲む。しかし――どんなに多く飲んでも――飲み手が楽しい酔心地でうとうとするほど飲んでも、杯の酒がなくならない。
こうしたことや、そのほかいろいろのことが、清朝の伝説に述べてあります。しかし、こうした伝説を書いた人たちが、蓬莱を、蜃気楼でなりと、見たとこがあるとは思われません。というのは、そこには食べた人がいつまでも飢や渇きを感ぜずにいられる、ふしぎな木の実もないし、――死人をよみがえらせる魔法の草も、――神泉も、――米のなくならぬ茶わんも、――酒のなくならぬ杯もないからです。蓬莱には悲しみも死もないというのはうそです、――冬はないというのもうそです。蓬莱の冬は寒く――冬の風は骨身にしみ、雪は恐ろしくうずたかく龍宮城の屋根にふり積みます。
しかし、蓬莱にはふしぎなことがいろいろあります。そして一ばんふしぎなことは、支那のどの作者も書いていません。それは蓬莱の大気ですが、それは蓬莱特有のもので、そのため、蓬莱に射す光線はよその光線よりは白い、――まぶしくない乳色の光、――おどろくばかりに透明で、しかもおだやかな光なのです。この大気は今の世のものとはちがう――とても遠い昔の大気で――その遠い昔のことを想ってみるとおそろしくなる位であります。そしてその大気は、窒素と酸素の混合物ではありません。それはまったく空気などでできているのではなく、魂魄なのです――幾億万代の人の魂がまじってできた大きな透明体なのです――われわれとはにてもにつかぬことを考えていたひとびとの魂なのです。誰にもせよ、人間が一どこの大気を吸うならば、魂魄はその人間の血の中にしみ通って体内の感覚を変え――人間の空間時間の観念をすっかり変えてしまう――こうして人間はただ魂魄の見たとおりに見、感じたとおりに感じ、考えたとおりに考えるよりほかなくなるのです。こうした感じかたの変化は眠のようにやさしいのですが、こんな感じ方でみた蓬莱は次のように記すことができるでしよう。――
――蓬莱では悪というものを知らぬから、蓬莱のひとびとは生れてから死ぬまでほおえんでいる――ただ神神が蓬莱のひとびとに悲しみを送る時、悲しみの消えさるまで顔をおおっているだけだ。蓬莱の民は皆お互に信じ合い、愛し合って、ぜんたいがまるで一家族のようである。――女の話は鳥の歌ににているが、それは心が鳥の魂のようにむじゃきだからである。――遊んでいるおとめらのたもとのさゆらぎは、やわらかな大きな翼のはばたきににている。蓬莱では、悲しみのほかにかくすものとてはないが、それは恥じることがないからだ。又全然錠をかけることがないが、それは盜みということがないからだ。恐れるものがないからだ。ひとびとは皆――死はまぬがれぬが――小神仙であるから蓬莱のものは、龍宮の御殿のほか、何もかも小さくて、古めかしくて、変っている。――又、この小神仙たちは、じっさい小さな茶わんで飯を食べ、よくよく小さな杯で酒を飲む。……
――こう見えるのは多くはあの魂魄の気をすったからでしょう――しかしみなそうとはいえません。亡きひとびとのここに残したふしぎな力というのは、ただ理想のみにある魅力、昔の望みの魅力にほかならないからです、――その望みのうちには多くのひとびとの胸の中に――無我の人の単純な美しい心の中に――婦人のやさしい心の中に果されたものがあります。……
――西洋の悪風が今蓬莱の上を吹きまくっています。そして、霊気は、悲しいかな、そのために委縮し去ろうとしています。今ではただきれはしや帯のようになって残っているだけです――あの日本画の山水の上に長くたなびいている輝いた雲の帯のようになって。これらの狭い霊気のきれはしの下に今でも蓬莱は見られる――が、ほかには見られないのです。……忘れてはならぬ、蓬莱は又蜃気楼といい――見きわめにくいまぼろしなのです。そして、そのまばろしは今消え失せようとしています――そして絵と詩と夢とのほかにはもうニどと現れることかないでしょう。……
1950(昭和25)年6月20日発行
入力:Yomi
2022年9月20日作成
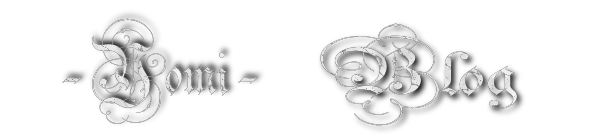



コメント