概要
小泉八雲著の「鏡と鐘」です。原題は”OF A MIRROR AND A BELL”です。
1904年に出版された小泉八雲著の『怪談』の中に収録されています。
本文
鏡と鐘
小泉 八雲 著
山宮 允 訳
八百年も前のこと、遠江の国無間山のお坊さんたちが、お寺の大鐘を鋳たいと思い、そのために、壇家の女しゅうに、地金にする唐金の鏡を寄進してくれろと申しました。
今でも、日本の寺庭に、そういう目的で寄進されたい唐金の鏡を見うけることがあります。私の今までに見た、こうした鏡の一番多く集めてあったところは、九州は博多の、さる浄土宗の寺の庭でしたが、その鏡は高さ三丈三尺の阿弥陀像を造るのに献げたものでした。
その頃無間山に若い百姓の妻が住んでいて、鐘の地金にするため寺に鏡を納めましたが、後になって、たいへんそれをくやしがりました。その妻は母親が前にその鏡について話したいろいろのことを思い出しました。そして、その鏡はただ自分の母親の持ちものだったばかりでなく、その又母親、曾祖母などの持物だったことを思い出しました。そしてその鏡にうつった嬉しそうな笑顔を思い出しました。もちろんその妻が鏡の代にいくらかの金を納めることができれば、この親ゆずりの鏡を取もどすことを願い出られたでもありましょうが、その必要な金がありませんでした。寺へゆくごとに、その妻は自分の鏡が柵の中に、いっしょに積みあげられた、なん百という他の鏡の中に交っているのを見ました。その妻はその裏に浮彫になっている松竹梅で、それがわかっていました――松、竹、梅というこの三つのめでたいしるしは、母がはじめてそれを見せてくれた時、幼児だったその妻の眼を喜ばせたものでありました。その妻はその鏡を持ち出してかくしておくようなおりがあればいと思いました――あといつまでも宝にしておけるように。しかしそのおりはありませんでした、――そしてその妻はたいへん気落して来ました――おろかにも自分の命の一部を人にやってしまったような気がしました。その妻は鏡は女の魂だという古いことわざを思いました――(そのことわざが「魂」という漢字で裏にふしぎにいい表わされてある鏡がたくさんあります)――そして、そのことわざが今まで、自分の思いも及ばなかった程、ふしぎに当っているとおもいましたが、自分の苦しい心を誰にもうちあけることはできませんでした。
さて、無間山の鐘のためにと寄進された鏡が残らず鍛冶場に送られた時、その中にどうしてもとけない鏡のあることが鐘師にわかりました。再三それをとかそうとしましたが、鏡はどうしてもとけません。きっとその鏡を寺に寄進したひとが、それを悔いていたにちがいありません。誠心をこめてそれを納めなかったので、その邪念が鏡に残っていて、鎔炉のただ中にあっても、鏡がかたく冷たくなっていたにちがいありません。
もちろん、誰もこのことを聞き知り、とけないのは誰の鏡であるかがすぐわかりました。そして、この心の中のきずが世間に暴露したために、あわれにもその女はたいへん恥ずかしく思い、たいへん怒りました。そして恥ずかしい思いに堪えられずに、次の文句のある書置きをして身投げしました――
「わたしが死んだら、鏡をとかしてを鋳ることはぞうさなくなる。が、その鐘を鳴らして割った人は、死んだわたしの魂のカで大金を授かる。」
実際怒って死ぬか、怒って自殺するかした人の、いまわのきわの望みや誓いは、人間業以上の力を持っていると世間の人が思っています。死んだ女の鏡がとかされ、鏡がしゅびよく鋳られてから、びとびとはその置きの言葉をい出しました。ひとびとはその書置きをした女が鐘を割った人にほんとうに大金を授けると思いました。そして、鐘を寺庭につるすと、すぐに鳴らそうとして大勢で押しかけました。ひとびとはあらんかぎりの力をこめて撞木をゆすぶりました。が、鐘はよくできていて、ひとびとの襲撃に勇敢に堪えていました。しかし、ひとびとは容易に落胆はしませんでした。毎日毎日どんな時でも、ひとびとは鐘をはげしくつきつづけ、坊さんたちの苦情など、少しも気にかけませんでした。こうして鐘の音に苦しめられることになり、坊さんたちはそれに堪えられなくなったので、とうとうそれを山からころがして沼に落して鐘を追っぱらいました。沼は深くて、鐘をのんでしまいました。――これが鐘の最後でした。ただ残っているのはその伝説だけですが、その伝説では鐘は『無言鐘』と呼ばれています。
さて、日本には古くから「なぞらえる」という動詞にそれとなくいい表わされている、ある精神作用のふしぎな力に対するきみような信仰があります。「なぞらえる」というその言葉は、英語のどんな言葉でもよくその意味が表わせない。それはこの言葉が信仰からする多くの宗教上の行事や、又、いろんな魔術がかったことに用いられるからです。辞典によると「なぞらえる」の普通の意味は「まねる」「たとえる」「にせる」などとあるけれども、奥底の意味は「ある魔術的、ないし奇蹟的の結果をもたらすように、心の中である物事を他の物事に代えること」なのです。
たとえば――自分に寺を建てる力はない。しかし、もし建てられる位の金持だったら建てようと思う信心で、仏像の前に一つの小石を供えることはわけなくできます。こうして小石一つ供える功徳は寺を一つ建てるのと同じ、あるいはほとんど同じなのであります。六千七百七十一巻の経文を読むことはできないが、それを収めた廻転文庫を作って、それを押して轆轤のように廻すことはできる。そこで、六千七百七十一巻をも読み得る程の熱心をこめて、それを押せば経文を読んで得られると同じ功徳を得られるのです。……「なぞらえる」の宗教的意味の説明は、まずこれで十分でありましょう。
魔術的意味はたくさんの例がなくては全部説明ができません。しかし、さしあたり、次の例で、まに合うでしょう。もし人が「ヘレンねえさま」が小さい蝋人形を造ったと同じ考えで小さなわら人形を造り――五寸以上ある釘で、丑の刻に社の杜にそれを釘づけにすれば――そして、わら人形で心にそれときめた人が、その後はげしく苦しみもだえて死ぬとすれば――それが「なぞらえる」の一つの意味のたとえになります。……又、夜中に盗人が人家に入って財物を持ち去ったとします。人がもし庭でその盜人の足跡を見つけて、その上に急いで大きな艾を点けることができれば、盜人の足のうらはほてってきて、盗人が自分で進んでもどって来て、あわれみを乞うまでは心が安まりません。これもまた「なぞらえる」という言葉で表わす魔術めいたことの一例で、その第三類は無間鐘のいろんな伝説によって例証されております。
鐘を沼にころがしこんだ後は、もちろん、それを割るほど鳴らすおりはもうなくなりました。しかしこのおりのなくなったことを、残念に思う人たちはよく、心の中でその鐘に代るいろんなものを打って割ろうとしました――こうして、大さわぎを起した鏡の持主の霊をなぐさめようとするのでした。そういう人たちのひとりに、梅ガ枝という女がありました――平家の武士梶原景季とのかかわり合いで、日本の伝説には名高い女であります。ふたりがいっしょに旅していた祈のこと、梶原がある日、金がないためにたいへん苦しいはめにおちいったことがありました。そこで梅ガ枝は無間鐘の伝説を思い出して、唐金の鉢を取りあげ、心にそれを鐘と思いなし、たたいてとうとう鉢を割りましたが、鉢をたたいている間、黄金三百枚をとなえ求めておりました。ふたりが泊っている旅籠屋のひとりのお客が、このたたく、わめくのわけをたずね、難儀話を聞いて、梅ガ枝に黄金三百枚をやりました。後になって梅ガ枝の鉢について一つの唄ができました。
梅ガ枝の手水鉢、たたいて
お金が出るならば……………
このできごとのあったあと、無間鐘はたいへん評判になり、大勢の人が梅ガ枝の例にならい、梅ガ枝の好運にあやかろうとしました。そうしたびとびとのうちに、ひとりの放蕩ものの百姓があって、無間山の近くの大井川のほとりに住んでいました。持物をふしだらな暮しに使いはたしたので、その百姓は、わが家の庭土で無間鐘の模型をつくり、その泥鐘をたたき割りましたが、たたいている間大金をとなえ求めておりました。
すると、眼の前の上の中から白装束の女の姿が浮びあがりました。長いみだれ髪をなびかせて、蓋のついた一つの甕を捧げていました。そして女はこういいました。
「わたしはあなたの熱心な祈りに答えに来ました、答えるねうちのある祈りだから。では、この甕をお取りなさい。」そういいながら、女は甕を男の手に渡して消え失せました。
男は、よろこんで、妻によい話を聞かせようと家の中へかけこみました。男は妻の目の前へその蓋のある甕――重い甕でした――をおきました、そして、ふたりで開けました。見れば、その中には一ぱい、口元まで……
だが、いけない!――私には実はそれに何が一ぱいはいっていたかお話できません。
1950(昭和25)年6月20日発行
入力:Yomi
2022年9月25日作成
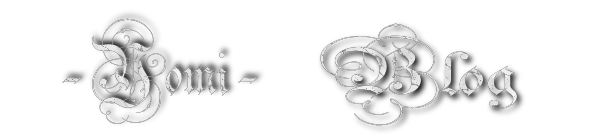



コメント